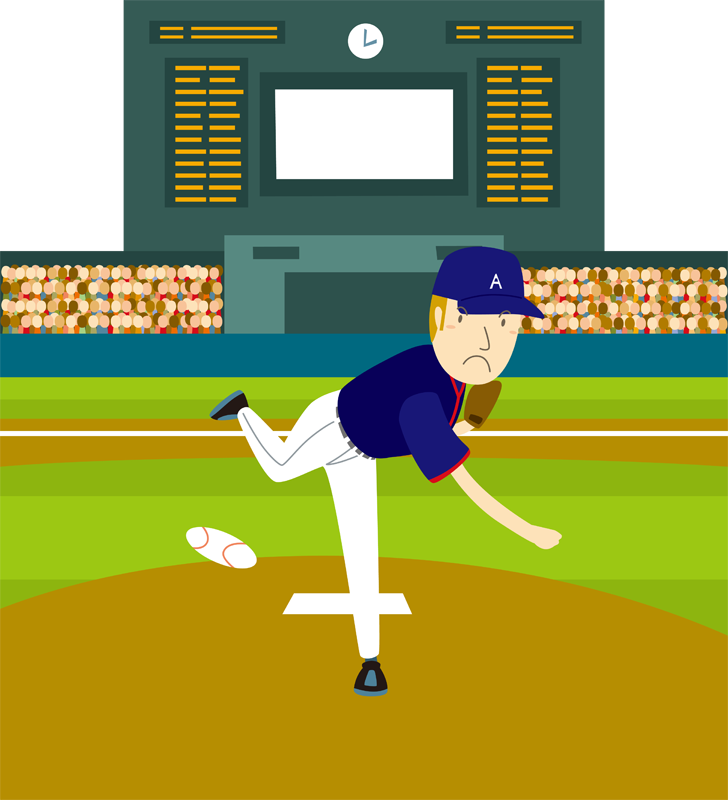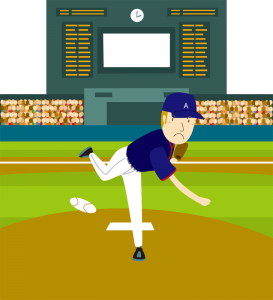
ピッチャーの投げる球速はスピードガンで測定しますが、どのような仕組みで測定するのでしょうか?
本記事ではスピードガンの仕組みと精度についてご紹介します。
スピードガン
スピードガンは動いている物体の速度を測定する装置です。
スピードガンという言葉は米国のディケイター・エレクトロニクスという会社の登録商標となっていて、英語ではレーダーガン(Radar gun)と呼ばれています。
プロ野球の試合でピッチャーの球速をスピードガンで測定するようになったのは、1979年からです。2004年からは高校野球の試合でも使用されるようになりました。
スピードガンの仕組み
スピードガンはドップラー効果という物理現象を利用しています。
ドップラー効果とは、例えば救急車が近づいて来る時、サイレンは高い音に聞こえますが、通り過ぎた後は低い音に聞こえる現象のことです。学校の理科か物理の授業で習ったことがあると思います。
音源から発せられる音の周波数fは音源が観測者に対してvの速さで近づいている場合、聞こえる周波数f’は以下の式で表されます。
f”=f×(V+v)/V …(1)
f:音源から発せられる音の周波数
f’:観測者が聞こえる音の周波数
V:音速
v:音源の移動する速さ
この式を変形して
v=V×(f’/f-1) …(2)
となります。
スピードガンで速度を計測する時は音の代わりに電磁波を使用します。
音も電磁波も同じ波の一種です。
音源がピッチャーが投げるボールに、観測者がスピードガンに相当します。
Vは電磁波の速度、fはスピードガンから照射する電磁波の周波数です。
スピードガンから照射した電磁波がボールに当たって、跳ね返ってきた電磁波をスピードガンで受信し、その周波数f’を測定することにより、(2)式よりボールの速度を測定することができます。
静止したボールに電磁波を当てると同じ周波数で反射し返ってきますが、動いているボールに電磁波を当てると、その方向に応じて周波数が変化し反射します。
その変化した周波数を検出することによりボールの速度を測定することができるのです。
スピードガン以外にも、車の速度違反の取り締まりに使われるオービスやゴルフのヘッドスピード測定機器なども同じ原理でドップラー効果を利用して測定されています。
スピードガンの測定精度
スピードガンで速度を測る場合、測定精度がよく問題になりますが、スピードガンを測定対象の進行方向の正面、または真後ろから測定する場合が一番正しく計測できます。
野球の場合ピッチャーとキャッチャーを結ぶ直線上でスピードガンを設置して測定すれば正確に測定できます。
この直線上からずれると誤差が生じます。ただ、遅い数字が出ることはあっても、速い数字が出ることはありません。
また、スピードガンの機種によっも測定精度は変わると思いますが、日本ではこのことは公表されていないので何とも分かりません。
以上、スピードガンの仕組みと測定精度についてご紹介しました。