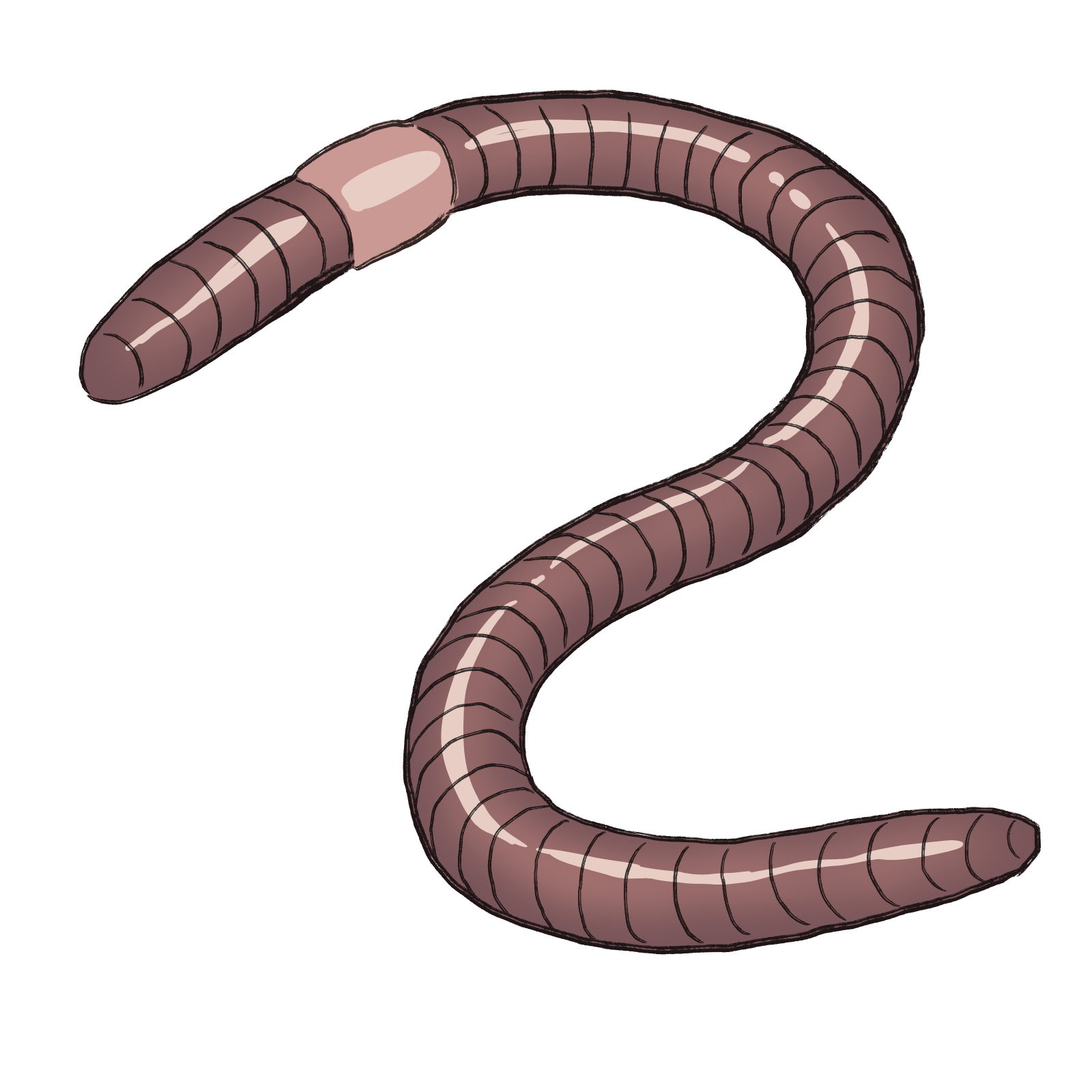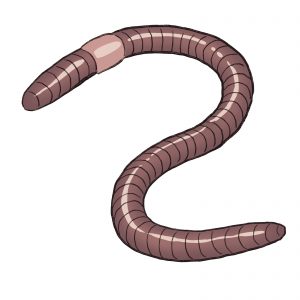
ミミズは「地球の虫」 (アースワーム )というスケールの大きい名前をもっています。
しかし、人間と長い付き合いがあるにもかかわらず、いつもは土の中にいるせいか、一般には必ずしも関心をもたれていません。
本記事では、ミミズは何類に属していて、どのような生態で、日本にはどのような種類のミミズが生息しているのかを記載しています。
ミミズは何類?
ミミズは、背骨のない無脊椎動物の中の環形動物門貧毛綱に属しています。
魚釣りのエサとなるゴカイや、人やペットの血を吸うヒルなども同じ環形動物門に属していて、ミミズとは近い関係にあります。
環形動物は、細長い体に体節があり、体節ごとに体壁、筋肉層、内臓があり、ミミズやゴカイ、ヒルなど、約15000種類が知られていて、土壌や水中、海中など、さまざまな環境に生息しています。
貧毛綱はミミズのことです。
これまで世界で知られているミミズの種類は約7000種、日本では約180種ともいわれていますが、ほとんど分類が進んでいない仲間もあり、明確な種類数はわかっていません。
ミミズの生態
ミミズの目や口は?
ミミズには目はありませんが、皮膚に散在する視細胞で明るさ程度は分かるようです。
動く時には、口の先にある舌のような部分を広げたり、左右に動かしたりして、周囲に何があるのかを探りながら動きます。
ミミズの背中と腹は?
ミミズの背中は黒っぽく、腹は白っぽいので、簡単に見分けることができ、背面を上にして移動します。
ミミズの体毛(剛毛)
ミミズの体は多くの体節がつながっていて、各体節には、フトミミズでは約50~100本の、ツリミミズでは8本の毛が生えています。
ミミズの呼吸
ミミズは、肺など呼吸の特別な器官をもっておらず、粘液で皮膚を常に湿らせ、その皮膚を通して酸素と炭酸ガスを交換します.
ミミズのオス、メス
ミミズはオスとメスの区別がない雌雄同体の生き物です。
そのため、広い土の世界でミミズ同士が出会った際、出会った2個体とも産卵することができ、効率的に子孫を残すことができます。1個体だけで産卵する種もいます。
ミミズの大きさ
ミミズの大きさは、ミズミミズのように1 mm以下の小さなものから、大きなものでは石川県から滋賀県にかけて生息しているハッタミミズのように60 cm以上のものもいます。
ミミズの進化
ミミズは、手や足、頭、触角など、目につく器官が体の表面に出ていないので、下等な動物と思われがちですが、同じ環形動物の仲間であるゴカイのような複雑な形態を持った祖先から、地中生活へ適応するために単純化する方向で進化したものと考えられています。
日本にいるミミズの種類
日本に生息するミミズは主にフトミミズ、ツリミミズ、ヒメミミズの3種類で、このうち95%以上をフトミミズが占めています。
フトミミズ
日本に生息するミミズのうち95%以上はフトミミズが占めています。
フトミミズは体長10センチほどのものが多く、体色は灰色から黒褐色で、畑では最もよく見られるミミズの種類です。
地中に穴を掘って巣穴を作って生活しているので、畑を耕している時に出てくるミミズは基本的にこの種類になります。
ツリミミズ
ツリミミズはフトミミズと同じく大型のミミズで、体色は灰色から黒褐色です。
フトミミズとツリミミズは、剛毛の数で見分けることができます。フトミミズの剛毛は一つの体節ごとに10本以上であり、ツリミミズは8本です。
ヒメミミズ
体長1~20mmほど、体色は乳自色から淡黄色です。
センチュウと見間違えられることが多く、また、しばしば腐敗した作物の根に付着していることから害動物とされることもあります。
体が多数の節と剛毛を備えることから、センチュウと区別できます。
ミミズは良い土を作る
ミミズが生息する土は良い土と言われています。
ミミズが土をかき混ぜることで土壌耕うん作用が働いて、土壌中の微生物の活動が活発化します。
また、サラサラの土をミミズが食べて糞をすることで、土は以前より大きな土の粒(団粒)になります。
土の団粒は植物にとって根が呼吸しやすくかつ、水はけが良くなりプラスの作用が働きます。
さらに、窒素の無機化が促進されることにより、植物の成長に貢献します。
このようなことから、ミミズは生活する周囲の環境を効果的に変化させる役割があり「生態系改変者」と呼ばれているそうです。
ミミズの名前の由来
ミミズには目がないので、目で見えないという意味から「目不見(メミズ)」が転じて「ミミズ」になったというものが一番よく知られている由来です。
また、ミミズは主に土の中で生活しているため、日光を感じるということがなく、日光には弱い生物です。このため、日を見ることがないということから「日見ず(ヒミズ)Jが転じてミミズになったという説もあります。
まとめ
ミミズの生物学上の分類や、生態、日本にいるミミズの種類などについてご紹介しました。
ミミズというと、その土壌効果や生ゴミなどの有機物を、ミミズと微生物の力を借りて、分解し、黒く、栄養価の高い堆肥変えるミミズコンポストが注目されていますが、最近では、イトミミズを使って田んぼの雑草を減らす研究やミミズが持つ心筋梗塞などの原因となる血栓を分解する酵素を利用した製品の開発も行われているそうです。
また、ミミズは体節と呼ばれる輪状の部位を縮めたり伸ばしたりして、ミズ特有のぜんどう運動と呼ばれる運動方法で移動しています。
この動きを忠実に再現したミミズロボットを開発して、管が細く複雑に入り組んでいるような下水管や工場の配管などの点検を可能にするような研究なども行われています。